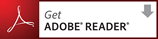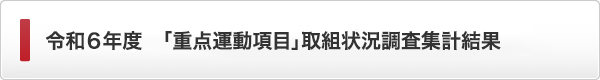
鹿児島県PTA連合会では,重点運動項目の「食育・一家庭一家訓・我が家の教育の日」及び「県P五つの実践」について,県内各単位PTAから実践状況のご報告をいただきました。
それぞれの項目において,家庭での語らいが増えたことや子どもたちの生活習慣に変容が見られること,会員の交流も増えることによりPTA活動・地域行事等が,少しずつ復活してきている状況が見られます。各単位PTAから寄せられた特色ある活動も掲載しましたので,今後の取組の参考にしていただけたらと思います。

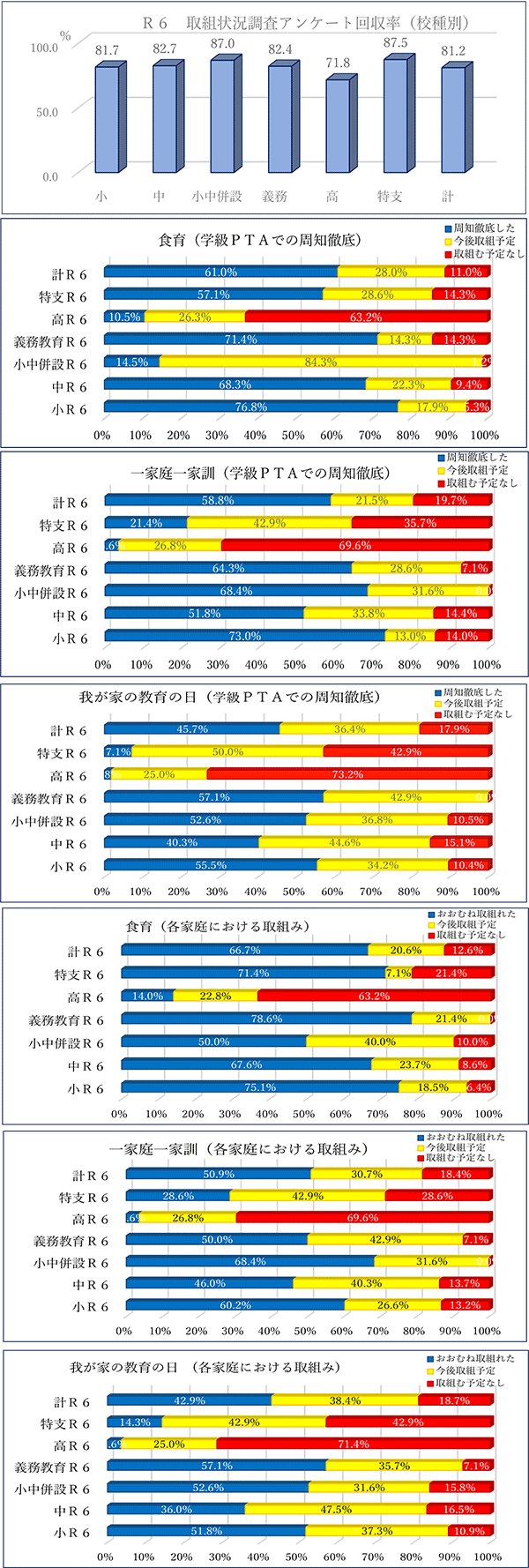
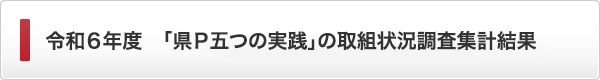
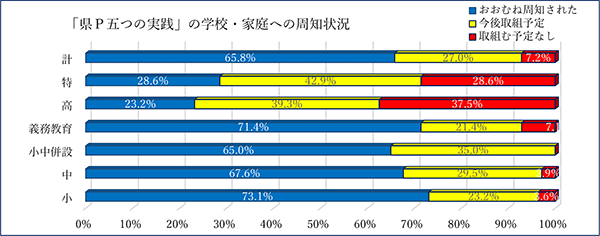
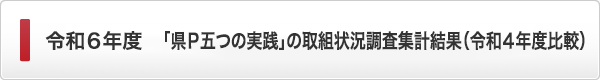
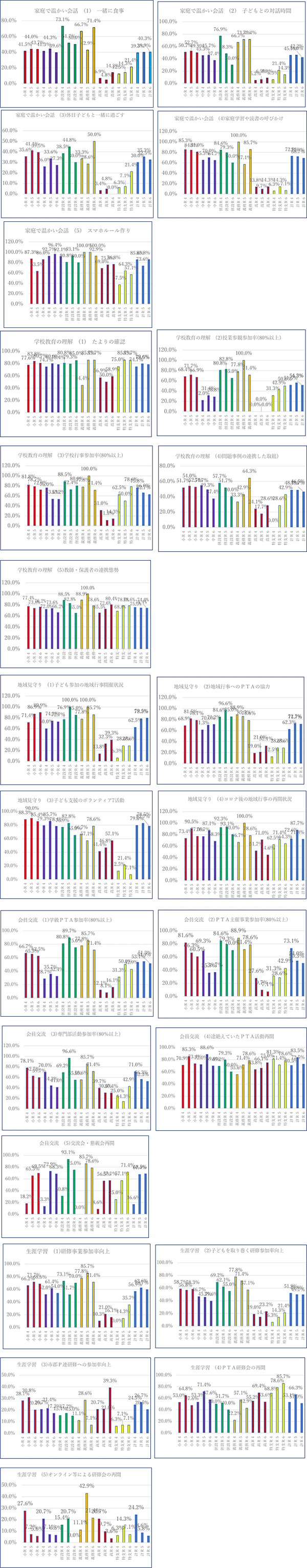
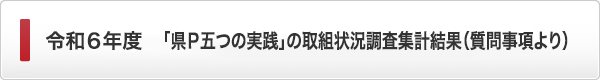
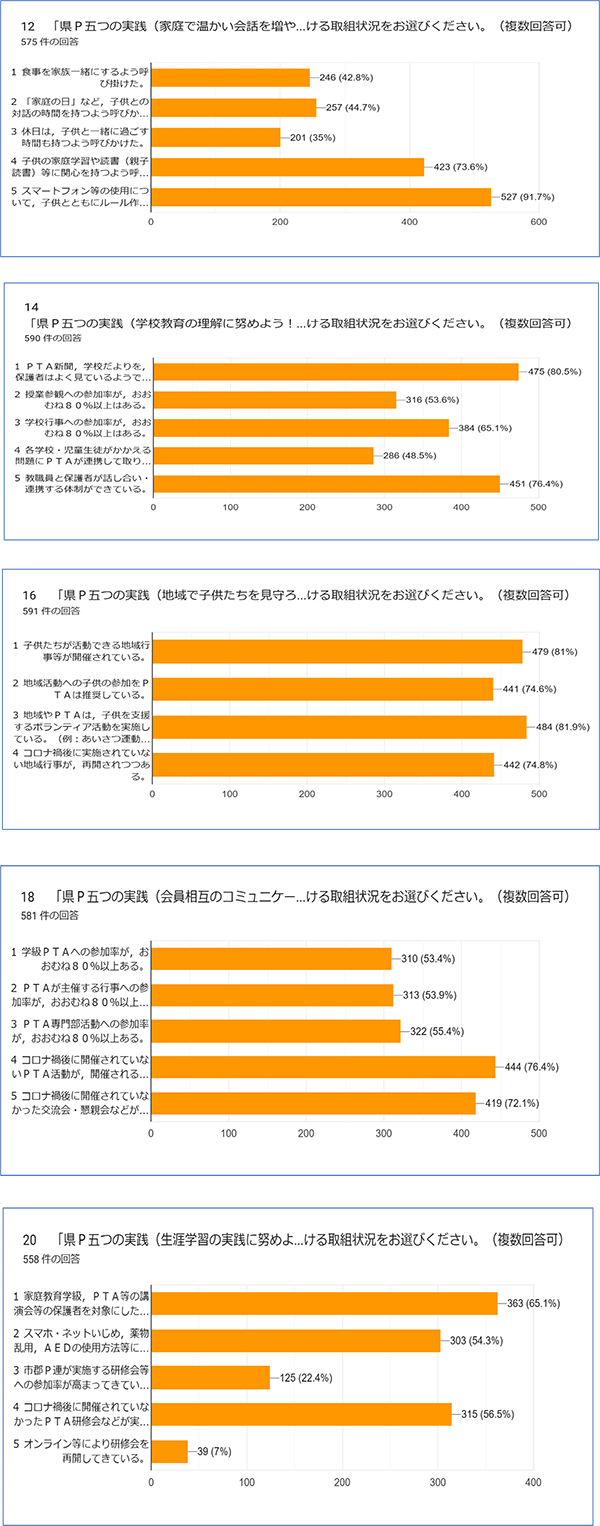
Ⅰ「食育」について具体的事例
【PTAの取組】
- PTAと連携して、学校田で田植え・稲刈り・脱穀等の米作り(もち米)に取り組んでいる。そ して、収穫したもち米を利用し、島民も招いてもち作り体験を実施し、最後にできた餅を皆で食べるようにしている。米作りを通して、親子ともに自分たちで育てた農作物を食す体験をすることができる。
- 栄養教諭による食育指導や家庭教育学級におけるタカエビ料理教室
- 家庭教育学級で魚さばき体験を計画
- PTA研修視察で給食センターに訪れ、所長や栄養教諭の話を聞き、調理室等の見学を行い、給食試食までさせていただいた。
- 入来地域PTAで子ども食堂を運営されている方の講義を行った。
- 学校保健委員会等と関連づけ朝食摂取調査等を行った。
- 学校保健委員会で食育についての講演会と簡単な調理をした。
- 親子おおすみおさかな教室を開催している
- 学校栄養士を招聘し、親子食育教室を実施
- 毎日朝ごはん運動の推進
- 学校の一年を通しての米づくりに参加する。
- 保健だより,学級PTA,学校保健会等を通して,保護者への啓発を図った。
- 栄養教諭を講師に招き,自分たちで育てた食材(いも・しいたけ等)を使って,調理実習をしている。
- 栄養教諭からバランスのよい食事について講話をしていただいた。
- 子どもが作るお弁当の日
家庭教育学級で、「子どもたちの食」というテーマで、町の保健センターの管理栄養士に講話をしてもらった。 - 学校保健委員会で「望ましい基本的生活習慣の確立をめざして」というテーマを定め,年間を通して全家庭で取り組んでいる。「望ましい基本的生活習慣」として,早寝,早起き,朝ご飯,歯磨きを位置づけ,学級PTAや学校保健委員会で取組状況を確認している。
- 栄養教諭を招聘し全学級で食育授業を実施しその様子を週報やブログで広報。家庭教育学級で民間の外部講師を招聘し食に関する学習会を開催。
- 今年度より一年生を対象に給食試食会を行う。保護者同士の交流の場にもなり、普段子どもたちが食べている給食の量や味付け、食材の大きさなど知ることができた。また、実際に子どもたちが食べている様子も見ることができた。
- 1年生保護者を中心に家庭教育学級において、給食試食会など食育に重点を置いた講義・体験学習を取り入れている。
- 家庭教育学級で栄養士を講師にお呼びして食育講座を開いた。
- 家族交流給食
- 家庭教育学級での食育講話
- 家庭教育学級における給食試食会(養護教諭による給食の説明)
- 保健だよりによる啓発
- 家庭教育学級:お魚捌き体験教室、育てたジャガイモで調理しよう
- 給食試食会、栄養教諭による授業、さつまいも・桜島大根の栽培
- 夏休みの課題として「かみかみメニュー」作りを課題として出している。
- 全体PTAで養護教諭が説明し, 「早寝・早起き・朝ごはん」を合言葉に全体で取り組んでいくことを確認した。
- 「早寝・早起き・朝ご飯」(特に「早起き・朝ご飯」)を推奨し、各学年PTAの努力目標に設定して実践している。
- PTA保体部が参加しての学校保健委員会で,講師を招聘し,「ミネラル」をテーマに講話
- 給食試食会を実施し,家庭でも栄養バランスの取れた食事をとるように,考える機会を設けた。
- 学校保健委員会(PTA保体部出席)での食育についての重要性を啓発し、その後行われる学級PTAでPTA保体部から周知する。
- 夏季休業中の課題の一つとして、親子で食事を作り、その様子を写真付きの記録としてまとめさせる取組を実践した。
- 学級PTA単位で、中学年は親子でクレープ作りを、高学年は宿泊し親子で夕食や朝食を作ることで食の大切さを学習した。
- 給食フェスタを実施し,学校における食育の取り組みを発信し,地域と連携した食育活動の推進を図る。
- 親子クッキングを行い、ロイロノートを使って、提出し 掲示をしている。
- 社会教育学級で学校栄養教諭を招いて、食育についての講演会を開いた。
- 学校保健委員会(年2回)において、食育の企画・推進を行った。
- 学校給食委員会を実施した。
- 夏休みに「健康レシピ親子クッキング」に全校で取り組み,選ばれたレシピ料理は,給食で提供している。
- 7月、小中学校PTA合同で朝食の大切さについて研修を行い,味噌玉作りを行った。
- 地元の川で獲れたアユを、川遊び体験時に食べる。
- 親子で食に関する講座を受講した後,給食試食会を実施している。
- 保健だよりやPTA懇談会で「食育」について取り上げて話し合った。
- 自分たちが育てた野菜の世話に収穫することで、食べ物を育てることの大切さや食品ロスについて保護者と共に考える(3年生)
- もちつき大会、芋ほり、焼き芋や保護者、地域と行うことで食べ物の大切さについて考えられるようにしている(全校)
- 献立表にコーナーを設けてお知らせしている。家庭教育学級で栄養教諭が紹介する。
- 家庭科のの長期休業中の課題で、「我が家の朝食」に取り組ませている。
- 子育ての悩みごと座談会を実施し、その中で子供の食事のマナーについて保護者同どうし話し合った。
- PTA新聞でお弁当の具材アンケート結果を載せるなど、食育に関連する話題を取り上げた。
- 保健体育部がプリントを配布、呼びかけをしている。
- 夏季休業中の親子クッキング、サツマイモ栽培とさつまいもを使った調理実習
- 学校保健委員会において、栄養教諭による「朝ご飯について」の講話を行った。
- 昨年度に引き続き、給食試食会を実施し、試食会を通じて食に関する知識や意見交換が幅広く出来ました。また昨年よりも新入生の保護者さんや父親の参加者が増えて良かった。
- 「早寝・早起き・朝ごはん」について、各家庭での取組状況を学級PTAで確認し合った。
- 12月の学校保健委員会で、朝食の重要性について町保健センターの職員から講話をいただく予定である。
- 親子食堂への参加
- 学校給食センターの視察・給食試食研修会
- PTA共通実践事項に取り入れている。
- 学校給食試食会を開催。学校給食センターから講師をお招きして、朝ごはんを食べることの大切さや、子供達が普段食べている給食がどのように作られているかを学び、給食を参加者全員で準備して食べる取り組みを行いました。
- 栄養教諭を講師とした家庭教育学級を実施し、親子で味噌玉作りをした。
- 「にこにこお弁当の日」(児童が主になって弁当を作る日),親子郷土料理教室
- 3年生では郷土料理を食改メンバーに教わる時間を作っている。2年生では学校菜園で安納芋を栽培、PTA愛校作業日に畑作りのサポートをした。
- 西姶良サポーターズ(旧おやじの会)や家庭教育学級が中心となり,稲作体験を実施している。
- 1・2年:生活科に育てたサツマイモ→焼き芋、3・4年:総合的な学習に育てたもち米→餅にして、育てることや感謝して食することにつながている。
- 包丁を持たせて切る 味付けまで 子供に任せる
- 子ども食堂,郷土料理作り
- 朝食レシピコンテスト
- 「家庭菜園で、みんなで楽しく食べる」「できるだけ手作り無添加のもの」「朝ごはんはしっかり食べて登校させてます。嫌いな食べ物も食卓に出された分は完食することを基本としてます」「夜ご飯は家族みんなで食べる」
【家庭内の取組】
- メディアの適切な使い方と関連付けて、朝食の摂取についても取り組んでいる。
- 早寝・早起・朝ごはんの実践
- 遠足の日は「お弁当の日」に親子で取り組む。
- 朝食・昼食を親子でつくろう
- 自分で作るお弁当の日を年1回設定し、家庭の協力をいただいている。
- 夏休みに親子で朝食作り
- 家庭での料理作りチャレンジ(長期休業)
- 郷土の伝統料理を親子で調理し、食しながら、理解を深める。
- 毎学期一回、家庭生活振返り週間を設定して朝食の意識啓発を図っている。
- 学校保健委員会で学校歯科医を講師に招聘
- 親子での米作り 餅つき体験 等
- 家庭での親子で料理(夏季休業課題として)
- 親子で一緒に調理等を行い、食卓を囲んだ。
- 団らんを大切に 残さず食べる
- 配布される給食だよりを家庭の話題とした。
- 一緒に撮る食事が温かいものになるように会話を心がけた。
- 朝ごはんをしっかり食べる 食事のマナーを守る
- 「ニコニコお弁当の日」として,子どもが保護者と一緒にお弁当を作るようにしている。
- 親子で作った朝ご飯のレシピや感想をまとめ紹介した。
- お箸ならべやテーブル拭きなど役割を決めて取り組めるようにする。
- 甘いものを食べすぎたり飲み過ぎたりしないと約束している。
- 親子で料理する。
- 3色の食べ物について話をしている。
- 家庭菜園のプランターでじゃがいもやほうれん草を作り,水やり等一緒にしている。
- 「いただきます」「ごちそうさま」を必ず言う。
- 配膳,下膳の手伝いを声かけしている。
- 弁当の日(地元の食材を使って自分で作った弁当を持ってくる)、食農学習(講話)
- 自分たちで収穫した筍を持ち帰り、各家庭で調理して食べる。
【学校の取組】
- 食育だより等での啓発
- 給食試食会(保護者対象、学校運営協議会委員対象)
- 栄養士による食の指導を受けた
- 土曜授業の日に親子講演会で食育をテーマで講演会を実施した。
- ソーセージ作り体験、栄養教諭出前授業(全学年)、虫歯予防教室
- 中・低学年での親子給食試食会や高学年での魚捌き方教室。
- 伝統野菜や農作物の栽培
- 給食試食会
- 12月の土曜授業で「お弁当の日」を実施予定
- 田植え、稲刈り等
- 早寝・早起き・朝ごはん・排泄を呼びかけ、健康チェックで項目ごとにチェックして意識化を図っている。
- 自分でつくるお弁当の日(年3回)
- 米作り・黒糖作り
- 遠足の日に「おにぎりお弁当の日」を設定している。
- 一年生が郷土料理について調べ、実際に調理を行った。
- 1年生保護者を対象に,食育講話,給食試食会,親子調理教室を実施している。
- 年間を通した「稲作活動」(田植え、稲刈り、脱穀、餅つき)
- 理科研究でSDGSを考えた食育を考えた。
- 霧島市健康増進課に出前講座を依頼した。
- 給食参観、試食会の実施
- 生活習慣チェック
- 地域の特産品のおお茶を通しての活動
- 朝食を取るよう呼びかけている
- 弁当の日
- 蕎麦の実を植えるところから、蕎麦にして食べるところまで行っている
- 「お弁当の日」を設定し、生徒が家族とお弁当を創る日を設けている
- 食育講話,給食試食会
- 自分達で作った米や大根、さつまいもを使って調理して食べる。
- 生徒が主体的に食に関心を持ち、家庭の食について保護者と語り合っている。
- 親子でお弁当作りの各家庭に資料配布。
- 朝食の大切さなどが書かれた掲示物。
- 学校保健委員会や学級PTA,学校だより等を利用して食育の啓発に努めた。
- 朝ご飯をたべる。
- 生活習慣振り返り週間
- 成長期の必要な栄養を豊富に含んだお手軽クッキング実習
- 野菜の栽培活動を行い,育てた野菜を使って調理活動を行う。
- 栄養教諭から個別の栄養指導を実施している
- 給食試食会や給食だよりでレシピを紹介している
- 地産地消を心がけている。
- 学校給食を活用した食育
- 夏休みの課題として親子で料理に取り組むものを設定した
- 月に1週の「健康生活調べ週間」において、早寝早起きや朝食の摂取、排便等について呼びかけ、チェックすることで意識化を図った。
- 新一年生保護者を対象に給食試食会を実施
- 給食の代わりに、お弁当の日を設けている。
- 本年度は3年生を対象に、校庭の一部を畑にしサツマイモの苗を植え付け、収穫、学校給食にて食すと言う取り組みを行なった。耕す行程や、植え付け、収穫の作業を学校応援団として地元の農家から協力をもらい、保護者と共に作業を行なった。収穫までの草取りや水やりは子供 たちが行い、食育に関する取り組みを地域と保護者で取り組むと共に、保護者は地域との「つながり」の大切さを学ぶことができた。
- 米と野菜を作っているので、手伝ってもらいながら食べ物のありがたさを話したりしている。
- 食育だよりの発行
- 弁当づくりの日(年4日)
- 自分たちで育てたもち米で餅つきをして食べる。
- 文化祭でミネラル不足による影響を、文献と合わせて紹介
- もち米作りを地域の方と行い収穫祭として餅つきをしている。
- 年に2回の生徒が自ら作る「お弁当の日」の開催
- PTA協力のもと,全校生徒によるジャガイモ栽培
- 県とタイアップした食育を中心とした健康管理に関する講話を実施した。
- 地元の窯元から提供された薩摩焼でいただくお茶碗給食
- JAや漁協と連携した体験授業や調理実習の開催。
- 一年生の保護者を対処に、給食試食会を11月に行っている。
- 栄養を考えバランス良く食事することの呼びかけ。
- 全Pを対象とした給食試食会における「食育」指導
- 親子ふれあい給食(給食試食会)の際に、栄養教諭より食育指導を行っている。
- 子どもたちが育てた餅米で,地域の方々と一緒に餅つきをして丸めて会食している。
- おにぎり給食(11月1日 食の大切さについて生徒に考えるために,生徒が各自でおにぎりを作り,給食時間に食べている)
【地域の取組】
- 朝食を摂ることの推進
- 栄養士の講話と親子料理教室をおこなった。
- 学校近くの水田で,地域の農家と連携して米を栽培するプロジェクトを実施している。収穫の喜びを感じる「イッシーまつり2025」や,収穫した米を使ったおにぎりコンテストを開催し,食べ物がどのように育つかを体感することで,食材のありがたさを学ぶことができる。
- 市が保護者向けに「食育に関するアンケート」を実施した
- 市P連母親部会が取り組んでいる 令和6年度 食育に関する事業「お助け朝ごはん」に参加し,親子で朝食の献立作りに取り組んだ。
- 市P連が行っている「朝食レシピコンテスト」への参加を促したり、長期休業中の家庭科の課題として料理に取り組んでもらったりしている。
Ⅱ「一家庭一家訓」についての具体的事例
【PTAの取組】
- 「一家庭一家訓」について、PTA全体会の場を利用して周知するとともに、一家庭一家訓を記して掲示するための用紙を配布した。
- メディアコントロールについて関することを家訓を考える
- 家庭教育学級で一家訓一家訓づくりを予定
- 学習発表会で全家庭の家訓を掲示する予定
- カードに記入し、家庭と学校に掲示している
- アウトメディアチャレンジ(選択して取り組む)
- 親子20分間読書
- PTA総会での家庭での3つの目標を共有し、学期ごとにアンケートを通じて取組について振り返りを行なっている。
- 早寝早起き朝ごはんが取組100%だった。
- 家訓の設定 → 家訓の可視化 → 日常での実践 → 振り返り
- 各学期末に、成果や課題の振り返りをPTAや学校評価の際に実施し、継続的な取り組みになるようにしている。
- 元日に拝賀式を行い、1年の抱負を発表している
- 用紙を準備し,各家庭,学校で掲示している。
- 我が家のスマホ・ゲームのルールを家族で話し合い,用紙に書き,それを家庭に掲示してもらっている。
- 朝家族であいさつを必ず行う
- 全家庭で取り組み,家訓を教室・廊下に掲示している。また,家庭でも掲示してもらい,意識化を図っている。
- 毎学期学級PTAで取組のようすを紹介していただいている。
- 我が家のルール作りを学校保健委員会や学級PTAで呼びかけ、各家庭で取り組んだ。
- タブレットやスマホの使用を21時までにする。
- PTA総会,家庭教育学級などでの確認 発表 校内での掲示
- 年度初めのPTA総会で取組について共通理解し,全家庭で「一家庭一家訓」を作成し各家庭で掲示して実践につなげている。また,学期ごとの学校評価の項目に入れたり学級PTAでの話題にしたりすることで各家庭での意識化を図ることができた。
- 年度初めの学級PTA で取り組みについて呼び掛け、実践している
- 6月中に全家庭に案内送付、PTA生活部で集約し、印刷して、会員に紹介。冬休み明けをめどに取り組み状況のアンケートを実施し、集約した結果を会員に報告する。
- PTA活動の1貫として取り入れており、全児童と保護者が一緒に取り組み、校内で学年ごとに良い作品を掲示し周知を図っている。
- 年度はじめに全家庭に設定してもらい、年間を通して実践してもらっている。(実践内容は全家庭分、校内に掲示)
- 年度当初の学級PTA,PTA総会の中で,各家庭で取り組むようにお願いをした。
- 親子で行事に参加しよう。
- 全家庭「一家庭一家訓」を作り,PTA新聞で紹介し合った。
- PTAの際に,状況を確認している。
- PTA総会で周知し、用紙を配布、家庭掲示を依頼している。
- 年度初めのPTAにて各学級単位で早寝・早起き、予習復習、読書、忘れ物ゼロなど年間を通して取り組む内容を決めている。
- 年度当初、生活面(生活部)や保健面(保体部)での設定・実践を各家庭にお願いしている
- 夏休みの一家庭一家訓として期間を決めて取り組み、結果を2学期のPTA新聞で公表した。
- 我が家の新年の抱負を冬休み(元旦)に考えてもらい、作品にして提出してもらう。
- 令和6年度PTA活動方針の重点事項として『家庭学習60・90運動』の推進を図った
- 自主的に動く 感謝する 挨拶、返事をしっかりと 一緒に楽しく食事をする
- 「楽しい子育て全国キャンペーン」~家族で話そう!我が家のルール・家族のきずな・命の大切さ~ 三行詩に取り組んだ。
- 年度当初に各家庭で実践することを決め、家庭掲示と学校掲示を行った。
- リビングのつく場所に貼って家族で確認できるようにしている。
- 夏休みに家族新聞を各家庭作成し、我が家の家訓を決めて、掲載している。
- PTA総会や学級PTA等で,各家庭で家訓を決めて取り組むよう呼びかけている。特にメディアとの関わりにおいて,親子で話し合ってルールを決めて守るようにした。
- 年度始めのPTA理事会でPTAテーマを設定し、その後、開かれる第1回の学級PTAで、それぞれの実態に合わせた親子で取り組む学級の目標を設定する。学期末の学級PTAで各家庭の取組を振り返り次に繋げていくようにしている。
- 項目を作り保護者へのアンケート実施。
【家庭の取組】
- 一家庭一家訓を全P戸数書いたものを玄関に掲示している。
- 家族全員で話し合って家訓を決定する。その後,子供たちが装飾した家訓をリビングなど目立つ場所に貼り,日常生活の中で挨拶や感謝の言葉を意識して実践する。月に一度,家訓の実践状況を振り返り,全員で改善点を共有することで,家庭内の協力と成長を促す。
- 年度初めに各家庭ごとに一家庭一家訓を設定し、家庭内・校舎内に掲示した。
- 玄関に各家庭の「一家訓」を掲示している。
- 毎日寝る前におやすみのハグ
- 子供と話すこと 5分でも遊ぶこと 自分と家族の大切さを教えてあげたい
- 元気よくあいさつをする。自分にできる手伝いをがんばる。
- 「はきものをそろえる」「午後9時メディアOff」「いつも明るいあいさつ(おはようございます)」等について各家庭で取り組んだ。
学校の取組
- 全家庭で取り組み,家訓を教室・廊下に掲示している。また,家庭でも掲示してもらい,意識化を図っている。
- 冬休みの宿題に「一家庭一家訓」を加え、年明けに家族で取り組んでもらっている。
- 学級ごとに1枚のシートにまとめ,学級に掲示している。
- 学校の掲示版に全家庭掲示している
- 家庭用と学校用とラミネート掲示を行い,取り組み状況についてアンケートを実施した。
- 一家庭一家訓を新年のスタートに合わせて作成するよう冬季休業中の課題にしている。
- 一家庭一家訓を5月の土曜授業(ふれあい参観日)で紹介し、児童玄関前の掲示板に一年間掲示している。
- 我が家の家訓をミニ掛け軸にして校内に掲示している。
- 毎週水曜日に実施している「元気チェック」や学期1回取り組んでいる「メディアダウンチャレンジ」での親子で目標設定
- 各家庭に書いてもらった物をラミネートして返却し,玄関等に掲示してもらっている。
- 本校の学校教育目標に合わせ,キャリア教育を軸とした一家庭一家訓を呼び掛けた。
例:「一日一善」,「自分でできることは自分でする」,「相手への思いやり,感謝が明日への幸せとなる。毎日楽しく生きる」,「感謝の気持ちを忘れずにありがとうを伝えよう」等。また,全家庭に提出してもらい,その後全家庭にお知らせしています。 - 中学校区で連携してメディアに対する家訓を決めて取り組んでいる。
- スマホの使用やライフプラン等について、家庭で語ってもらうように学校としてお願いしたい。
- 4月:一家庭一家訓を決め、各家庭で取り組む。9月・2月:学級で振り返りを行う。
- 「おうしゅう運動」に一家庭一家訓(うちなりのルール作り)を位置付けて推進している。
- 全家庭が一家庭一家訓を作成・提出し,学校で掲示
- 子供のための社会ルール30の実践
- 3校(谷山中・谷山小・西谷山小)で「安心安全にインターネットや情報通信機器を利用できる環境づくり」について、取り組み親子できまりについて考える場の設定を継続している。
- 家訓を募集し、カレンダーを作っている。
- 授業参観後に,親子で「一家庭一家訓」について確認する時間を設定し,全校児童の前で,親子紹介も兼ねて発表した。
- 市の取組の「一自慢」や家庭学習60・90運動も形式に加え、家庭だけでなく校内にも掲示した。
- 各家庭に用紙を配付し、記入してもらったものを校内に掲示している。
- 家庭教育学級で「子供の成長とメディアの影響」について、町保健センターの保健師に講話を行なってもらい、各家庭でメディアとのつきあい方に関心を高めることができた。(親子でノーメディアの実施やSNS8時オフなどの取組が見られた。)
- 学校の年間行事予定表の中に、「一家庭一家訓」を記入するスペースを設け、家庭に掲示してもらうように呼びかけた。
- 全校児童の一家庭一家訓を校内に掲示して、忘れないようにしている。
- 各家庭でメディアに関するルールを決めて実践している。
(平日ゲーム禁止は共通実践事項) - 学校と家庭共に掲示用ポスターを作成し,学校内には1年間掲示した。
Ⅲ「我が家の教育の日」について具体的事例
【PTAの取組】
- 家庭学習90分以上取り組み,見届ける。親子で語る(学校の様子等)時間 など
- 家読、人権標語など
- 親子で一緒に学習する時間を作り,子供が学校で学んだ内容を復習する。保護者が宿題をサポートし,質問に答えることで学習理解を深める。
- 読書の日,ストレッチ運動,親子でメディアコントロール
- 毎月、家族読書の日を設定している。
- 子育て三行詩への応募
- 各学級PTAで年間テーマを設定し学校と家庭が連携して取組を進めている。
- PTA総会で周知した。各家庭では、「我が家の家訓」の他、「一家庭一運動」「食育」などに取り組んだ。
- メディアを停止し、夕食の準備・団らん等の時間を家庭で過ごす
- 今後の学級PTA等の中で周知していきたいと思う。
- 学校保健委員会の中で、児童生徒・保護者も交えて、学校全体の取組内容を決めた。また、各家庭でも読書の日や学習の日を設定した。
【家庭内の取組】
- 週一回は,家族で語り合う場を作るように呼びかけている。将来の話や学校生活,友達等について,テーマを決めて語る。
- 親子での対話、ふれあい活動の推進
- 家庭学習の見守り
- 小中連携の取組で,中学校の定期テストの期間に「我が家の教育の日(かめサンデー)」として家庭学習に家庭で取り組むようにしている。
- 毎月23日の「本城読書の日」や「メディアダウンチャレンジ」での親子での取組
- 家族で食事をとる。親子で運動 親子で読書
- 新聞の南風録を書写して、読めない漢字や分からない言葉を家族で話し合っている。
- 「学校であった出来事を話そう」ということ。
- 親子で一緒に食事をとる。
- 家族で大掃除に取り組む。
- 家読(家庭の読書)の推進
- 夫婦で子供に対して困った事や気になる事があれば、情報共有や家族で話す場を設けている。
【学校の取組】
- 各学期に1回、家庭学習の充実に関する取り組み強化週間を設定している。
- 家庭学習がんばり週間を設け、カードに記入しながら意欲的に家庭学習に取り組ませ、習慣化を目指している。
- 小中連携の取組として「家庭学習充実週間」を設定している。
- チェックシート「山崎ッズ」による親子の反省,担任の見届け
- 毎月23日は「親子読書・ノーメディアの日」を設定し,取組を呼びかけている。
- 学校の定期テストの日に合わせて、家庭学習の習慣付けを行った。
- 生活リズムチェック 歯磨きに関する啓発
- 夏休み期間に家族で運動を行う取組。メディア利用に関する家庭での約束を決める取組。
- 中学校の中間・期末テスト期間に合わせ,下西スリーアップ週間を定め,「基本的な生活習慣」「家庭学習習慣」「親子読書習慣」の3つの習慣を向上させる取り組みと体力つくりについての取組を家庭と連携しながら取り組んでいる。
- 親子10分間学習の啓発
- 親子読書の日(毎月23日)を設定し、読書カードを記入して掲示している。
- 家庭学習強調週間を設定して,毎学期1週間家庭学習の習慣化に努めている。期間中は,チェックシートを配布し,学習時間や生活時間を親子でチェックすることで,家庭学習の習慣化や学習環境の充実を図っている。
- 毎月19日~23日に健康貯金通帳を記録し、生活習慣の改善に努めている
- 各家庭での過ごし方の呼びかけについて
- ふうだな(大棚)の子3つのめあて振り返り日の設定
- 学力向上週間(中学校テスト期間にあわせて設定)を実施し、家庭での見届け確認をお願いしている。
- 読書推進の一環で,MBCアナウンサー二見いすず様をお呼びして親子参加の絵本朗読会を行った。
- 各学期1回ずつ定期テスト前にノーメディア週間を設定。校区内小学校も同時に実施。
- 家庭と連携した「60・90運動」の推進
- 宅習強調週間の実践(年間4回)
- 学期に1回、学力向上週間を設定しており、生活習慣や学習習慣を見直すためにチャレンジシートを配布し、家庭での取組を振り返る機会にしている。
- 一小一中であることから,中学校の定期テスト期間にメディアコントロールに取り組んだ。
- メディア(テレビやゲーム、インターネット等)の利用時間をチェックすることでメディアコントロールの意識化を図った。
- 「家庭学習強調週間」を学期1回実施。各学年に応じて、めやす時間以上の家庭学習、メディア視聴の時間を減らして読書や家事の手伝いをする、生活リズムチェックをとおして家庭における学習の習慣化の確立を図る。
- 我が家の教育計画を冬休み(元旦)に考えてもらい、作品にして提出してもらう。
- 相手の気持ちになって考え、意見を言い合う 家庭学習の見届け ノーメディアデー
- 毎月23日を家庭の日として設定し、家読カードにおすすめの本の紹介を書いて学校の掲示板に掲示している。
- 中学校の期末テストに合わせて実施している学習習慣定着に向けた取組「花丸ウィーク」に合わせて、日頃の宿題以外の自主課題や読者などを進めている。
- 中学校と連携して,中学校のテスト前に「家庭学習強調週間」を設定し,家庭へ積極的な取組を呼び掛けている。
- 毎学期家庭学習強調週間を設定し、家庭での時間の使い方、ノーメディアデーの取組等を行っている。
- 毎月23日は、「読書の日」を設定し、読書記録には家庭からの一言を書いてもらっている。また、家庭学習強化週間にファイルにて取り組み状況を確認してもらっている。
- 「読書」「ニュースについて話す」「一日一回はお手伝いをする」「お風呂の掃除を順番にする」「ペットの世話。メディアの時間を減らして読書」
Ⅳ「家庭で温かい会話を増やそう!」について参考となる事例
【PTAの取組】
- 学校キャンプを実施し、親子で一緒にカレー作りなどに取り組み、調理後は皆で一緒に輪になって食事をした。
- 家庭教育学級にて、子供とのコミュニケーションについて講演会を予定している。
- 各学級で取り組むテーマを設定し、親子で運動する時間を確保するなど取り組んでいる。
- 学校・家庭・本人で月1回トライアングルほめ日記に取り組んでいる。
- 学校保健委員会の取組の一環で,「親子でエクササイズ」に取り組んでいる。
- 家庭教育学級における子育てサロンの実施
- 家庭の日標語募集に作品提出
- 家庭教育学級の一環として,歩こう会・親子クッキングをすることで,親子で活動する時間を設けている。
- 学校保健委員会の取組として「家族会議(睡眠について)」を実施。
- PTA保体部を中心にスマートフォン、タブレットなど就寝時刻1時間前の電源OFFなど、学年ごとにテーマを決め、子供と一緒に親も守っていけるよう声掛け及び学級PTAで振り返りを行っている。
- 家読の日(毎月23日)を活用して,読書を通じて会話を増やすことに努めている。
- PTA三行詩の実践
- 校内夏祭りを通して、会員相互のコミュニケーションを深めたり、親子で参加し、楽しむことができた。
- 家庭で一人一役の役割を決め,みんなで励ましあいながら家事をしよう。
- 家庭教育学級で子供との会話についての講話を行った。
- 親子読書の日を毎月実施
- 各種通信等で話題となる学校の取組等を紹介し、家庭での会話を呼びかけている。
- PTA新聞に特集記事を組む
- 全体PTAで,規則正しい生活とメディア利用の仕方を振り返ると同時に,家庭内での会話を大切にしていくことを呼び掛けた。
- 絵本ライブを親子で鑑賞
- 情報端末9時預かり。
- 「親から子へ」(1、3年生全員)「子から親へ」(2、3年生保護者全員)のメッセージをまとめた「絆」の発刊
- メディアとの付き合い方についてPTA懇談会で話し合った。
- 毎月23日はアウトメディアの日として家族団らんの時間を設定することを学級PTA等で共通理解して取り組んでいる。
- スマートフォンの使用については、PTA総会において、生徒指導部からルールなどについて説明した。
- 保体部を中心に、元気ハツラツの取り組みアンケートを実施。
その中で、各家庭メディアを時間を減らし、親子のコミュニケーションを広げようとしたノーメディアデーの設定 - 毎月23日を「家読の日」とし、親子で読書を行い、感想等を伝えあい、対話をする時間を持つように呼びかけた。
- スマートフォン等SNSの使用について、学年・学級PTAの中で呼びかけた。
- 毎月「読書の日」を設定し、ノーメディアの取組を推進
- 子ども会と連携し,親子で活動できる企画を実施しいている。
【家庭の取組】
- いっしょに朝ご飯を作るなど親子での活動を取り入れている
- 毎月1週間、学習習慣や生活習慣調べ等を各家庭で実践している。学校で音読カード等を作成し保護者に確認をしてもらっている。
- 親子体操を実施した。
- 車での送り迎えの間、普段話さない父親と子供が話す機会として話題を用意している。
- 各家庭で子どもと過ごす時間が生活サイクルの中で確保されているため,親子の会話が日常的に多い地域である。
- 「ただいま」「おはよう」の挨拶の時,手と手を合わせてタッチをする。
- ドライブに行き,車内での会話を楽しむ。
- 家族で予算を決めて休みの計画をたてる。
- 家族で散歩をし、会話をしながら歩く。
- 地域行事にも家族で参加し、家族内はもちろんであるが他家庭との会話も行事を通して深めるようになってきた。
- 「学校での出来事を話し出したら、しっかり聞くようにしている」「テレビを消して、今日あったことを話す」「みんなで食事と会話をするために一緒に食事をしたり、一緒に過ごす時間を増やす」
【学校の取組】
- 家庭学習について振り返る時間を作るよう周知し,期間後各家庭コメントを書いて提出した。
- 家庭教育学級と児童の学習活動と兼ねたり、学校ブログを頻繁に載せたりして、話題を増やした。
- 学校図書を保護者も借りれるように取り組み、親子で共通の話題を持てるようにしています
- 小中連携部会で共通実践事項を決めて取り組んでいる。
- 学校であったことを保護者に話す機会を作ることや、学校からのお便りを確実に保護者に渡すよう連絡袋を改めて全児童に配布した。
- 学校行事での子どもの姿や家庭学習の取組あど称賛や励ましを呼びかけている
- 日曜参観における,親子ふれあい活動(R6年度ドッジビー)を設定することで,親子で楽しく運動できる環境づくりをしている。
- 阿久根市内で三中学校による中学生会議を実施し,メディア機器の取り扱いについて『保護者とルールを決め,使用する』となり,各家庭でルール作りを行い,実行した。
- テスト期間中にノーメディアデーを実施し,各家庭の実態に応じたメディアとの付き合い方を実施した。
- 毎月23日を親子読書の日として学校をあげて取組を行っている。
- 学校行事や家庭学習等の取組に対する励ましや称賛の呼びかけ
- ノーメディア週間を設け、各家庭でルールを決めて取り組んでいる。
- 日々、自分と友達に″3S”(さすが・すごい・すばらしい)
- 学校だよりで家庭の日の周知をはかっている。
- 中学校単位で家庭学習強調週間として取り組み,その中で,アウトメディア(食事中にメディアを使用しない)を設定して,メディアを使用する時間を減らし,家族とのふれあいの時間を大切にしようと決めている。
①あいさつは必ずする。②自分が言われて気持ちの良くない言葉は使わない。※「言霊」を大事にしている。 - あいさつの輪を広げる標語への取組,表彰,広報
- 毎月23日の親子読書の日に,ノーメデイアデーを実施し,読書活動の中で実施
「うちどくカード」を配付し,「毎月23日は親子で読書」を呼び掛けている。 - 地域コミュニティと連携して、親子で参加できる行事を実施することで、自然と会話をする機会を設けることにつながった。
- 地域行事への参加を促した
- メデイアから離れて家族で過ごす時間の確保を呼びかけている。
- 食事中は、ノーディアにする。
- 家庭学習強調週間の取組の中に,家庭との時間を増やす。
- 中学校区(中学校1校、小学校2校)で、中学校の定期考査期間に合わせて家庭学習強調週間を設定し、学習や読書など取り組むようにした。
Ⅴ「学校教育の理解に努めよう!」について参考となる事例
【PTAの取組】
- PTA行事を地域へ呼びかけ協力を得ている
- 月1回程度PTA役員会を設け,情報交換を行っている。
- 学校保健委員会の取組促進
- 進路講演会の後援(講師の選定)
- 紙媒体だけでなくX(Twitter)や「学びポケット」などSNSも利用している。
- 学校に保護者が出向いて話をするだけでなく、SNSなども使いながら学校・PTA・保護者が負担なくつながれるように工夫している。
- PTA役員会を年5回実施
- 小規模校である本校では、役員数を減らし、全員がすべての活動に関わっている。
- PTA主催の親子レクリエーションや学校行事の運動会等において,保護者,地域,学校が連携した活動を進めている。
- 全保護者で分担し,全校児童への絵本の読み聞かせ活動を年6回実施している。また,保護者・地域の方々が協力して奉仕作業や運動会準備に取り組んでいる。
- 学校施設の美化活動や行事の準備などで学校に人手や道具が必要な時は,PTAを中心に協力体制ができている。
- 実際に見ないと先生方の苦労や有難さは理解できないと思っている。感謝している。
- 学校教育に関わる諸課題をもとに,PTA広報部と学校が連携してPTA新聞を作成しながら学校教育の理解を深める一手立てとしている。
- PTA朝の交通指導の取組(学期始め)
- 学級PTAが単に連絡事項の確認にならずに、保護者間の交流の場になるように、学級の役員と担任で確認している。
- 年2回親子奉仕作業を実施し、学校の環境整備に努めている。
- 年2回資源リサイクル活動を実施し、子供たちの教育活動の支援に努めている。
- 学校からの配布物やブログを通じて、行事や進路、保健、図書に関することなどを発信している。
- 教員と保護者の間の意見や疑問をPTAが一緒になって検討し、教員と保護者のコミュニケーション不足を補う役割を推進している。
- PTA理事会・役員会を定期的に開き、共通理解・実践に取り組んでいる。
- 学級PTAがある日に全体PTAを開催し,保護者と学校が連携し話し合う場を設定。
- 学校参観日には、必ず全体PTAを開催している。
- 家庭教育学級で、市教委のサポートをいただきながら、児童生徒がタブレットを用いて取り組んでいるAIドリル「キュビナ」について、学んだ。
- Classi等の活用での呼びかけなど
- 中学校区3校のPTA合同理事会において、各校の実践について交流したり、共通実践事項を定めたりしている。
- 「授業参観やPTAへのできる限り出席」「学校だより、通信などをよく読む」
【家庭の取組】
- メディアとの関わりについて期間をもうけて家庭で取り組んでもらっている
- 学校であったことを子供に聞いている。
- 学校のホームページをチェックする。
- お金の使い方について親子で考える「親子マネーセミナー」の実施
【学校の取組】
- 全家庭、必ず学期ごとに一回は、担任と個別相談をする機会を設けている。
- 学校ブログ、ホームページの活用
- 全体PTA,学校運営協議会,地域学校協働活動,家庭教育学級の理解を深める。
- 第2土曜日の3校時をフリー参観として設定。保護者へ参観を呼びかけている。
- 授業参観週間や学校行事等の日程を各種通信だけでなく、集落放送を利用し、保護者への周知徹底を図っている。
- 学校行事やPTAや授業参観日以外に、毎月3・4日を「佐志の日」として保護者や地域の授業公開日・学校参観日と設定し、気軽に学校に足を運んでもらう日にしている。
- 学校生活アンケート(学期1回実施)
- 授業連動型家庭学習の見届け,行事・行事準備の協力・協働。
- 学校評価委員会、コンソーシアム会期、地域協働推進など多角的に取り組んでいる。
- 11月県民週間での参観の呼びかけ、地域の方への学校だよりの配布
- 親子協働活動を数多く学校行事に組み入れている
- 集落(字)の放送等による地域の方への学校行事等の案内
- 地域の方への学校便りの配布
- 学校ホームページ・ブログの周知と定期的更新
- 学校からのお知らせの周知徹底のために一斉メールを活用して、『はい』『いいえ』の確認をしている。
- 学級通信や学校だよりを必ず読もう。
- ブログの更新に努め、学校の様子を伝えている。
- 11月の学校自由参観日の周知、教育相談等の充実、プール掃除や運動会会場準備をPTAと連携して進めている
- 学校運営協議会に参加し、意見交換をしている。
- 毎年、本校で研究公開を行い、PTAもボランティア等で参加している。
- 家庭学習強調週間(中学校定期テスト前の期間、市内小学校とも連携して取り組む)
- 学校見学会と同時開催する福祉機器展示会を、保護者にも公開。PTA総会でニーズを把握し、保護者にお知らせして、今年の11月1日に実施。寄宿舎の送迎に合わせることで多くの参加があり、視覚障害教の理解に繋がった。
- Instagramやブログで学校の様子を紹介
- コミュニュティスクールを設置し、地域の代表者からのご意見をもらい教育環境の見直しを実践している
- 保護者以外の地域の方に,授業参観や学校行事に参加して頂いている。
- 学校のインスタも活用して、生徒の学校生活の様子や情報を発信している。また、学校安心メールも活用されている。
- 県民週間の日の授業参観
- 行事参観など。
- 学校ホームページ(ブログ)にて,情報発信を積極的に行っている。
- 体育大会、文化祭への保護者の積極的参加
Ⅵ「地域で子どもたちを見守ろう!」について参考となる事例
【PTAの取組】
- PTAで地引き網を開催し、地域の方にも手伝いをいただいている
- 5・6年生を対象に,3泊4日校区公民館を利用して宿泊をする「ふるさと学寮」を行っている。地域や保護者の方々の協力のもと,食事やもらい湯,学習会などを実施している。
- 単位あいご会が活動できないため、コミュニティ、学校、PTA、校区あいご会それぞれの活動ではなく、まとまって「ホタルを見る会」や「校区ウォーキング」などを協力して開催している。
- PTAや地域の方による生徒の登下校の見守り活動(あいさつ運動)
- 地域ボランティアとの連携
- 家庭との連携に「学びポケット」を活用し、相互の情報提供ができるようにして、防犯連絡等に活用している。
- 地域にあるいろいろな団体で行事を計画し、学校も計画の段階から関わっている。
- PTA通学路パトロール 集団下校 危険箇所まっぷ
- 山川港まつりのパレードに参加し、地域へ創立50周年であることやPTAの紹介ができた。
- 毎週金曜日は、保護者によるあいさつ運動、登校指導を行っている。
- 登下校指導、街頭補導の実施、安心メールを利用して安全に関わる注意喚起の発信
- 今年から、お弁当を持参して、地域を含めて運動会を開催した。
- 立志の集い、餅つき大会等
- 災害に備える備蓄品をPTAで購入予定です
- 年に1回,PTAと地域と合同で危険箇所の確認や意見交換会を実施し,連携して子どもを見守る体制づくりに取り組んでいる。また,警察(駐在),民生委員,地域ボランティアの方々が連携して登校時の立証指導に取り組んでいる。
- PTAバザーを放課後ディサービス等の事業所へ参加の声かけをし,利用する子供と参加してもらった。
- 街頭補導の実施、朝の立哨指導
- PTA保体部を中心に,妙円寺詣り相撲大会に向けて取り組んだ。
- 子どもたちへの声かけ・見守り活動
- 学校行事を実施する際に、地域住民によるサポート・安全確保への協力
- 地域ごとに月1回のクリーン作戦を行っている。地域ごとに伝統の踊りがあり,夏季休業中や週休日に練習を行い,運動会で披露できた。
- 地区PTA:レクリエーション・茶話会・懇親会、地区PTA:通学バスバス停清掃
- 青少年育成協議会と連携をしたあいさつ運動の実施
- PTA主催の夏祭りで出店を準備したり抽選会を行ったりしている。子供たちによるステージ発表などもあり地域の方にとっても楽しいひと時となっている。
- PTA保体部を中心に、補導活動等を行っている。
【学校の取組】
- 本校は,特色ある教育活動の一環として「ゲートボールに親しもう」という活動を行っている。そこで地域の方々との接点が増え,普段から子どもたちを地域の方々が見守ってくださる環境にある。
【地域の取組】
- 島全体となって、夏祭りの縁日体験を子供にさせるための、「口之島夕涼み会」というイベントを毎年7月に実施している。
- みどりの少年団
- ミシンボランティアに民生委員が協力。民生委員、社会を明るくする運動、日本善行会など、地域の方々が挨拶立哨運動をしている。
- 地域関係者を対象とした学校教育懇談会にて、校区安全マップの見直しを行った。
- 合同運動会、地域のふれあいの会
- 地域と一緒に運動会を行ったり、敬老会を行ったりしている。
- 校区青少年健全育成連絡会の実施(年2回)
- 育成会で毎年ボーリング大会が行われている
- 校区コミュニティスクールの活動で、子ども達の声で録音した見守りに関する放送を、校区内で青パトの協力をいただきながら放送している。
- 学校運営協議会,地域学校協働活動
- 朝の交通指導、あいさつの日の立哨指導
- 地元NPOによる「地元のワクワク」をテーマにした授業を開催。移住者ら保護者が参加して体験授業を行った。11月に2回目を予定。
- 緑の少年団活動や学校林の管理などに地域の方の協力をたくさんいただいています。
- 地域の方々が毎朝登校時に立哨活動
- 豊年祭等の地域行事への推奨。集中する日は午後から下校とした。令和6年度10月21日,徳之島町立亀津中学校運動会や学習発表会は地域と合同で開催したり、町の夏祭りや綱引き大会を地域とPTAが連携して児童が参加したり、地域と学校が一体となり学校づくりを推進している。コミュニティスクールとして学校運絵に地域の声を積極的に生かしている。
- 地域塾の開催、育成会による老人会との交流行事
- 本校は伝統的(21年目)にエイサーに取り組んでいる。各小学校区の夏祭りや地域行事等でエイサーを踊っている。
- 先生方が地域行事に積極的に参加くださり、地域に身近な学校を実践し、地域との意思疎通を図っていただいている
- 「3のつく日のあいさつ運動」として,毎月3のつく日に,校区のコミュニティの方々や民生委員,保護者が参加して立証指導を行っている。子供たちの登校の様子を見守ったり,日頃の様子の情報交換をしたりしている。
- 地域学校協働活動,高千穂小元気塾。
- 民生委員、地域ボランティによる登下校時の見守り活動
- 子ども食堂
- 地域協働を通し学校、保護者、生徒、地域の連携を深める活動を様々実践している。
- 朝,不定期ではあるが地域コミュニティ協議会会長が立哨指導に加わってくださったり,地域の方が散歩がてら子供たちと一緒に登校してくださったりする。
- 豊年祭への参加(相撲等)
- コメ作りや川祭り、納涼祭の実施
- 車にはる防犯ステッカーを校区の有志の方々に配布し校区内を走行するときは掲示してもらっている
- 地域のパトロール隊が第2土曜日に立哨指導をしてくださっている。
- 校区校外補導。青少年健全育成会への参加。
- 島民の全員が島内の子供の顔と家を知るくらい,子供ひとりひとりが地域に認知され見守られている。
- 地域がえび・かに放流を企画し、その際に児童の交通安全を呼びかけている。
- 毎朝の交通立哨を行ってもらっている
- 6年生地域の高齢者とのグランドゴルフ、4年生妙円寺遠行での地域の方見守り
- 各種団体によるあいさつ運動やパトロール
- 夢講話 学校応援団
- 児童と地域コミュニティ、通学保護員、民生委員、保護司との交流会をしている。
- 校区で夏祭りを行ったり,子供育成会が中心となって鬼火焚きを実施したりしている。
- 学校行事に地域の方々が、積極的に関わっている。
- 各集落の行事に他の集落からも意欲的に参加する姿が見られる。
- 防犯パトロールや110番の家等で子供たちの見守りをしてくださっている方を紹介し、お礼を伝える機会として、「パトロール出発式」を毎年行っている。
- 青パト隊や校区公民館の児童の登下校時の見守りや学校運営協議会との連携
- 市民清掃の日に積極的に参加するよう呼びかけている。
- 呼びかけなくても敬老会等の地域行事への子供の参加が当たり前のこととして根付いている
- 地域活動(上小原スポーツフェスタ、奉仕作業など)に参加
Ⅶ「会員相互のコミュニケーションを深めよう!」について参考となる事例
【PTAの取組】
- 運動会を島全体の行事として実施し、運動会後の懇親会も島民全員参加で実施している。
- 家庭教育学級にて今年度,子育て座談会を開いた。
- 全ての学級が年1回学級レクリエーションを実施
- PTA主催のスポーツ大会を開催予定
- 世界(記録)に挑戦 「紙飛行機飛ばし(親路の会)」「ハイタッチ(運動会)」
- PTA役員メンバーで懇親会を行うなどしてコミュニケーションをはかる機会を設けた。
- 中学校区(小学校・中学校)におけるPTA会員交流活動(スポーツ活動など)
- 各学級PTA主催での夏休みレクも積極的に企画・開催された。
- 集落の清掃活動、運動会
- 会員全員がグループラインでつながっており,相談や連絡がスムーズにできている。
- PTA学級委員長を中心にサップ体験やバーベキュー等の交流の場を設定した。
- PTA専門部を学年部で組織しているため,コミュニケーションが図りやすい。
- PTAスポーツ大会の実施
- PTA歓送迎会の実施。PTA奉仕作業(年2回)
- 保護者が中心となり各学級で親子レクリエーションを年1回開催している。
- 親睦ソフトバレーボール大会を開催し、多くの参加があった
- 家庭教育学級,学級レク,愛校作業の実施。PTA共有のクラウド上のドライブの設置。
- 手軽なレクレーション、ふれあい活動、ヨガ教室等
- 高校見学ツアーや家庭教育学級の講座の実施
- 4校区合同レクリエーション大会の実施
- 年1回のPTA主催の「校長杯バレーボール大会」を実施している。
- コロナ禍で実施されていなかった学級PTAを全学年で実施できるようになり、クラスにおける保護者が関わる機会ともなっている。
- 安心メール等による行事等の連絡・確認
- 学級PTAの時間では、必ず「懇談」の場を設定し、保護者同士が語り合う機会をもてるようにしている。
- PTA主催の親子ふれあい活動
- おやじの会、マミーズ、PTA研修会などの参加を通して、横の繋がりができつつある
- 地域のあいご会を通して触れ合うこと。
- 学年PTAごとの親子レクリエーションの取り組み。
- 地域の祭りにて踊り連への参加、相撲行事の参加、親子学級レクリエーションの実施
- 学級PTAのグループワーク
- 親子ふれあいレクや餅つき大会,門松づくり等,親子で参加できる行事を実施し,親子だけではなく,会員同士の親睦も深めている。
- PTA親睦ミニバレーボール大会
- 海や山,台風や噴火など,自然と向き合いながら互いに知恵を出し合って子供にとって安全な生活環境づくりに努めている。地域行事を通じて地域の活性化や子供たちへの文化の伝承に努めている。
- PTAバサーを放課後ディサービス等の事業所にも参加の呼びかけをし,利用する子供と参加してもらった。
- 親子,職員参加のボウリング大会を実施している。
- 同級生の保護者や他学年の保護者で昼食会を設定し,情報を共有したり情報交換などしたりしている。
- 教職員の歓迎会や運動会の懇親会を地域の公民館で開き、地域の方々の参加も呼び掛けている。また、六月灯や学習発表会、県民週間や持久走大会の応援・立哨も地域ぐるみである。
- コロナ禍でも小学校PTA行事は中止することなく継続をしてきた。
- 諸会議の導入での構成的グループエンカウンターの実施
- 島内夏祭りが開催されて、PTAもブースを設けて、かき氷などを配った。
- グランドゴルフ,ゲートボール大会を通しての,学校・家庭・地域の交流の場の設定
- 串良地域7校PTA懇親会を開催した。
- 父親の会,母親の会を募り,活動を計画している。
- 各学年の担任と連携したレクを実施
- 全学級でのPTA学級レクリエーションの実施
- PTA執行部主催のそうめん流しの実施
- 学校保健委員会で県のスクールカウンセラーの先生を講師に招き、SOSの受け方についての講話を予定している。
- 学級レクリエーションを全学年で実施し、保護者間や親子間の交流の場を設けている。
- 各クラスから3名ずつ選出された役員が、それぞれの専門部(生活部・進学部・厚生研修部)へ所属し、行事の企画・運営に携わっている。
- PTA行事として、おはら祭への参加。また、「セゴドンノエンコ」と題して、PTAの協力をもらいながら、郷土の偉人について学ぶ遠行を行っている。
- 学級レクリエーション 親子ふれあいスポーツ大会 など
- 家庭教育学級への全家庭参加
- 歓迎会や里山フェスの開催
- 夏休みの週末にホラーナイトを実施。集落ごとに親子でブースを作り、おばけハントやコース巡りを楽しむことができた。
- 学級レクリエーションの充実に努め、予算配当を行っている。
- 文化祭や遠行等でのボランティアの協力等
- おやじの会が活発に活動している。
- 歓送迎会、懇親会など、負担のない程度での実施を検討している。
- PTAへの積極的な参加、委員長などを一度は引き受けるようにしている
【学校の取組】
- 各学年で保護者が中心となり「教育を語る会」と題して、生徒、保護者、教職員がレクリエーションなどによって交流図っている。生徒がこれからの目標を発表する場も設けられている。
- 手話学習会の実施(月1〜2回)
Ⅷ「生涯学習の実践に努めよう!」について参考となる事例
【PTAの取組】
- 県民大学講座に学校からオンラインで、職員・保護者・島民が参加できる体制をとっている。
- 出来ることをできる範囲で行っています。そのために、見直し等含めて精査しています。
- 会員が参加したくなるような内容の家庭教育学級研修視察を計画している。
- 救急救命法の学習会の実施(PTA)
- 家庭教育学級の開催時期や内容などを前年度の反省やアンケート結果を生かして変更することで,参加者が増えている。
- 家庭教育学級の内容に応じて,全学年への参加呼びかけ。
- PTA会員で分担して研修会へ参加している、PTA会員で進んで地域行事等へ参加している(港祭り、温泉祭り等)
- 地域高齢者大学の活用
- 進路についての研修会や研修視察を行っている
- 情報端末機器の危険性を認識して,よりよい人生を送るための道具としてみんなでつながれたらと考えている。
- 研修会の開催が増えてきている。
- 家庭教育学級の充実に努めている。家庭教育学級で作成した作品を学校の文化祭や町の文化祭に出展した。
- 学校保健委員会と連携し,健康・安全についての研修会を実施している。
- 「メディアと健康」で、ネット環境が及ぼす健康被害についての講話を聞く。
- 家庭の時間を確保できるように,休日の外出,帰宅時間を地域で共通理解する。
- 出された課題を終えてから遊ぶ等,家庭でのルールづくりと実践に努める。
- 児童数減少に伴い、保護者も減少。共働き世帯の増加によりPTA主催の研修会や事業に参加しにくい現状がある。働き方という名の下で先生方の負担軽減も考慮しなければならない現状もある中、保護者は「公休」や「有給」を使って各事業に「子どもの為」参加している。また、参加率80%を目指すと言うことは、一定の強制感が必要であるが、私たちはPTA参加における「強制感」を無くす努力に努めている。
- 強制感を無くし、「参加したい」と言う気持ちを作るPTAの風土も必要と考える。
- 強い参加率を求めるが故に、保護者は仕事を休む。職場によっては、市内小中のPTA行事が重なる事で、休みを希望する人が増え。職場への影響がでて来ることもある。
- PTA研修部を中心に,保護者のニーズに即した創意工夫された講演会や家庭教育学級の充実が図られている。
- PTA保体部による「健康に関する学習会」講演会実施、PTA研修部による「障害基礎年金について」講演会実施
- PTA教育講演会を実施した。今年度はパフォーマンスアーティストのK@ITOさんを講師に招き、「夢を伝えて」を演題として親子で講演会を楽しむことができた。
- 卒業生の保護者を招いての進路座談会や、大学見学の研修、市p連・県p連主催の研修会への参加など、希望者を募り多数の参加がみられた。
- 安心安全ネットワーク会議に生活指導部参加
【家庭の取組】
- 学校卒業後何がしたいのか子供と時々話をしている。
【学校の取組】
- デジタルリテラシー教室(メディアと健康との関係)の実施
- さまざまな社会教育の行事を、まなびポケットで積極的にPTAに向け紹介している。
- 地域にある施設(令和6年度は、気象庁の測候所)への親子での見学会を実施し、学びを深めたり、キャリア教育の観点で捉えたりできた。
【地域の取組】
- 地区・市の研修会に分担出席している。
- 地域コミュニティ主催の伝統行事への積極的な参加(門松・しめ縄作りなど)
- 地域コミュニティ主催の六月燈・門松づくりやしめ縄づくり等、伝統行事への積極的な参加